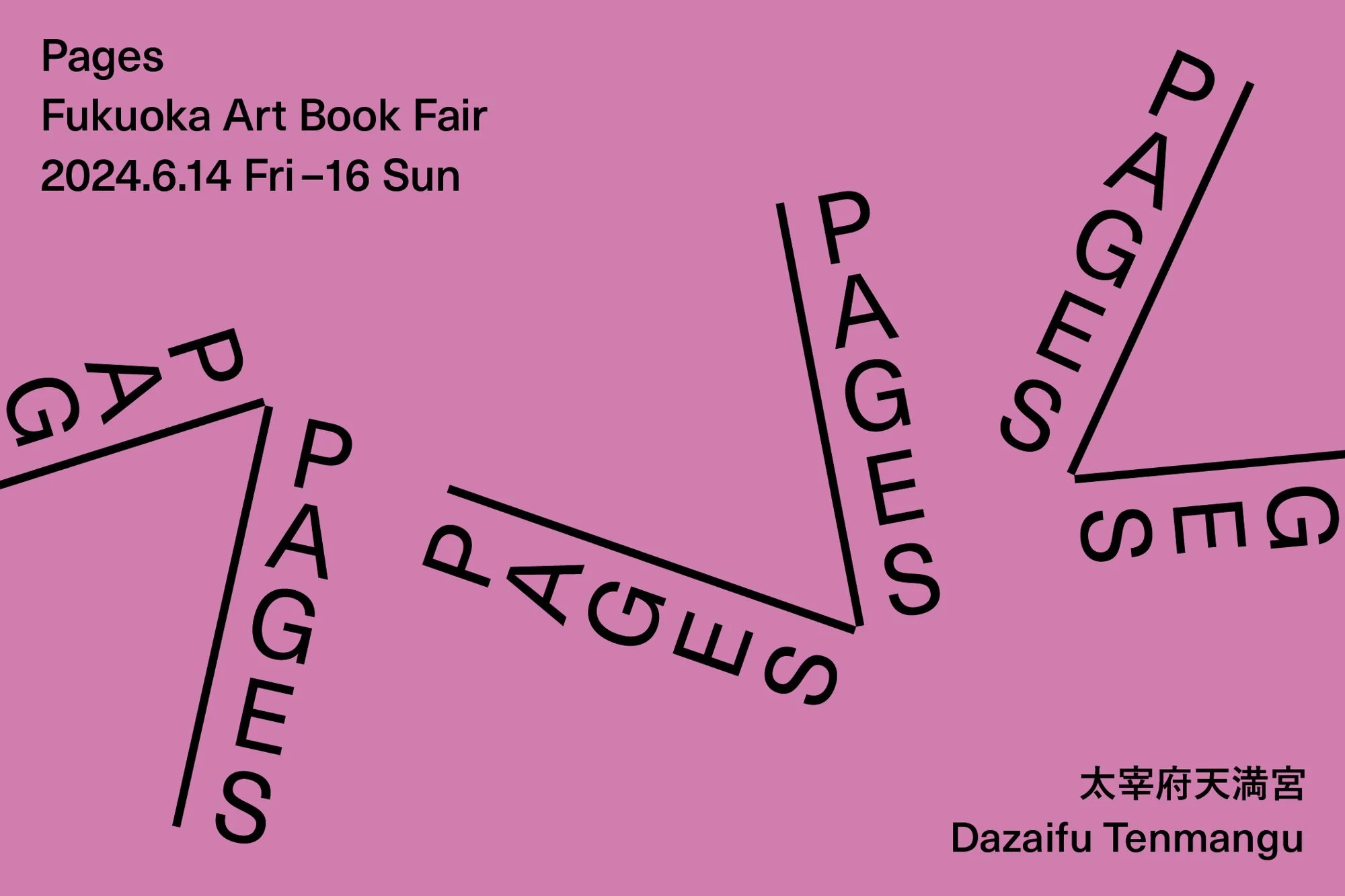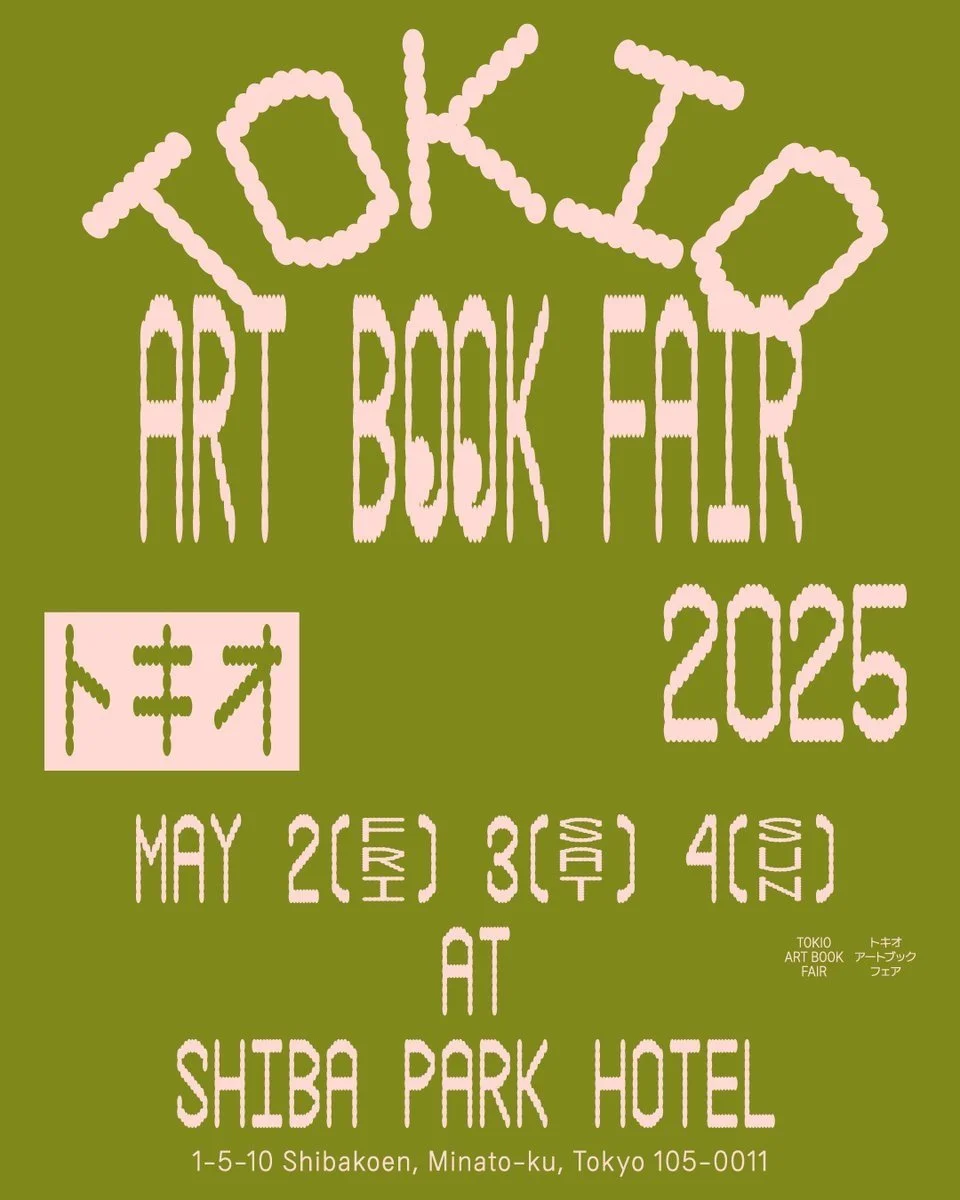Editorial Studio 1: Innovation
エディトリアル・スタジオの最初のセッションは、出版、考察、交流に根ざしたプロジェクトを始めるのにふさわしい場である Fukuoka Art Book Fair で開催されます。
この対談では、Studio The Future と 三好剛平 が共に議論をリードします。彼らは、幅広い参加者とともに、「イノベーション」というテーマを探求します。これは自明のものではなく、再考に値する言葉です。
「イノベーション」そのものが、解決策としてしばしば称賛される時代に、私たちは今一度立ち止まり、問いかけたいのです。
何かを「イノベーティブ(革新的)」と言うとき、実際にそれは何を意味しているのでしょうか?「イノベーション」は常に私たちにとって有益なのでしょうか?そして、「イノベーション」と見なされるものを誰が定義するのでしょうか?
単に新しさを称賛するのではなく、このセッションでは、進歩や変革という言葉に内在する価値観や前提について、慎重に考える機会を提供します。
Fukuoka Art Book Fairにおけるエディトリアル・スタジオは、対話そのものが文化的介入の一形態になり得るという信念に基づく、会話、矛盾、そして集団的探求のための空間です。
April 18, 2025
Pages / Fukuoka Art Book Fair
Fukuoka
detailed information about the session
- coming soon
The first session of The Editorial Studio takes place at the Fukuoka Art Book Fair, a fitting context to begin a project rooted in publishing, reflection, and exchange.
This conversation brings together Studio The Future and Gohey Miyoshi as the two lead participants. Together with a wider group of contributors, they will explore the theme of “Innovation”—not as a given, but as a term worth reconsidering.
In a time when innovation is frequently celebrated as a solution in itself, we want to pause and ask:
What do we actually mean when we say something is innovative?
Does innovation always serve us?And who defines what counts as innovation?
Rather than celebrating newness for its own sake, this session invites participants to think carefully about the values and assumptions embedded in the language of progress and transformation.
The Editorial Studio at Fukuoka Art Book Fair is a space for conversation, contradiction, and collective inquiry—anchored in the belief that dialogue itself can be a form of cultural intervention.
Editorial Studio 2: Contradiction
エディトリアル・スタジオの第2回セッションは、東京アートブックフェアで開催されました。本というメディア、デザイン、言語の文化的な役割を問い直すには、このような開かれた公共の場がふさわしいと考えました。
このセッションでは、サンドラ・カッセナールと木村俊正をリード参加者に迎え、狩野大輔(neutral colours)、古賀稔章(武蔵野美術大学)、Tjobo Kho(Outline Platform)、Cleo Tsw(Off Course)、Studio The Futureが参加し、デザイン、アート、教育、出版といった領域を横断しながら、多角的に議論を展開しました。
今回のテーマは「矛盾」。その緊張感から出発しつつ、それを否定するのではなく、むしろ問いとして抱えることから始めました。
このセッションで問いかけたのは、多くの人が日常的に感じている矛盾そのものです。
「よりよい暮らしのためにデザインする」と言いながら、今日のデザインは私たちの生活からますます遠ざかってはいないか?
デザインは本当に誰のためのものなのか?そして誰がその“デザイン”を行っているのか?
現代の私たちの生活は、個々のデザイナーによってではなく、プラットフォーム、制度、経済的構造といった大きなシステムによって形づくられています。もしデザインが「つくること」と「人々のためになること」の両方を内包する営みだとしたら、そこには大きなズレが生じているのかもしれません。
しかし、矛盾は必ずしも解消すべきものではありません。
むしろそれは、対話や想像力を促し、思考を動かし続ける力になり得ます。心地よくはないかもしれませんが、最も人間らしい状態のひとつであり、私たちに新しい視点を与えてくれるのです。
東京アートブックフェアでのエディトリアル・スタジオは、共に問い、ずれを抱えながら考える場として開かれました。文化における「矛盾」は、欠陥ではなく、むしろ創造を動かすエンジンかもしれません。
May 3, 2025
TOKIO Art Book Fair
Tokyo
detailed information about the session
- coming soon
The second session of The Editorial Studio takes place at the Tokyo Art Book Fair, an active public setting for questioning the cultural function of publishing, design, and language.
This conversation brings together Sandra Kassenaar and Kimura Toshimasa as the two lead participants. They are joined by Daisuke Kano (neutral colours), Toshiaki Koga (Musashino Art University), Tjobo Kho (Outline Platform), Cleo Tsw (Off Course), and Vincent Schipper (Studio The Future)—a group of practitioners working across design, art, education, and publishing.
Together, they will explore the theme of “Contradiction”—starting from its tension, but not ending there.
The contradiction at the heart of this session is one many of us live with:
How can we design for the betterment of life, when design feels increasingly disconnected from how our lives are actually shaped?
If design is meant to serve people, who are those people? And who is really doing the designing?
Our daily lives are increasingly shaped not by individual designers, but by systems—platforms, policies, and economic structures—that are far larger than us. This disconnect reveals a contradiction between purpose and power, between agency and influence.
But contradiction does not always need to be resolved. In this session, we ask whether contradiction might actually keep things alive—fueling dialogue, difference, and imagination. It may be one of the most deeply human conditions: uncomfortable, but generative.
The Editorial Studio at Tokyo Art Book Fair is a space for shared questioning and creative friction—anchored in the belief that contradiction is not a flaw in culture, but part of what drives it.
Editorial Studio 3: Perspectives
福岡で「イノベーション」という言葉そのものを問い、東京で「矛盾」をテーマに思考の余白を探ったエディトリアル・スタジオ。第3回となる今回は、**「視点(Perspective)」**に焦点を当てます。
会場となるTiger Mountainは、東京にあるエディトリアル・デザインに特化したスペースです。ただの会場ではなく、今回のテーマを象徴するような場所でもあります。
エディトリアル・デザインとは、単なる表現手法ではなく「ものの見方」を問う行為です。距離を取り、文脈を俯瞰し、複数の視点から物語や構造を読み解くこと。その本質は、まさにこのセッションが目指す問いと重なります。
リード参加者は、OneWorld編集長のセアダ・ヌールフセンと、編集者でありWorksightのコンテンツ・チーフ、そしてTiger Mountainの主宰者である若林恵。
出版、ジャーナリズム、デザインといった分野で活動する他の参加者たちとともに、「視点」はいかにして形づくられ、選ばれ、排除されるのかを探ります。
万博のような国際的イベントは、しばしば「包括性」「進歩」「協働」を謳います。
しかし、その語りは誰によって、誰のためにつくられているのでしょうか?
本当に多様な視点が反映されているのか?それとも、見えやすく、語られやすい視点ばかりが繰り返されているのか?
そして、語られなかった視点は、どこへ行くのでしょうか?
第1回ではイノベーションという言葉を解体し、第2回では矛盾を抱えることの可能性を考えました。第3回の今回は、**私たちはどこから世界を見ているのか?そしてその「見方」にはどんな責任があるのか?**を問います。
視点は中立ではありません。可視化されるか、されないか——それを左右するのは、構造であり、制度であり、力の配置です。
このセッションでは、次のような問いを共有します:
支配的な語りはどのようにしてつくられるのか?
エディトリアルな実践は、それにどう対抗できるのか?
異なる世界観に本当に耳を傾けるには、どんな準備と姿勢が必要なのか?
すべてのセッションと同様、本対話も両面刷りのポスターとして記録されます。一方にはビジュアル解釈を、もう一方にはテキストを掲載し、進行中の思考のアーカイブに加えていきます。
エディトリアル・スタジオ 第3回は、私たちが何を見るのか、ではなく、どのように見るのか、なぜそう見てしまうのか、そして他の見方を本当に開くには何が必要かを問い直すための場です。
May 24, 2025
Tiger Mountain
Tokyo
detailed information about the session
- coming soon
After beginning in Fukuoka with questions about innovation—and continuing in Tokyo with a reflection on contradiction—Editorial Studio 3 turns to the idea of perspective.
This session takes place at Tiger Mountain, a space in Tokyo dedicated to editorial design. More than a venue, it reflects the session’s core concern. Editorial design is not simply a matter of presentation—it is a way of thinking. It demands distance, not detachment: the ability to step back in order to construct a more holistic, multi-layered understanding of what is being told, shown, or left out.
Editorial design is fundamentally about multiplicity. It refuses single viewpoints and insists on looking at things from all directions. In this sense, it aligns with the central concern of this session: how perspective is shaped, claimed, and made visible.
The conversation is led by Seada Nourhussen, editor-in-chief of OneWorld, and Kei Wakabayashi, editor, content chief of Worksight, and head of Tiger Mountain. Together with contributors from publishing, journalism, and design, they explore what perspectives are made possible—or impossible—within events like the World Expo.
Such events often promote an image of global inclusivity. But in practice, what perspectives are actually represented? Who is invited in? Who is left out? And what happens to those whose worldviews do not align with dominant narratives?
If the first Editorial Studio questioned the language of innovation, and the second considered contradiction as a generative condition, this third session turns its attention to representation, marginalisation, and editorial responsibility.
Perspective is not neutral—it is curated, enabled, and constrained by structures of visibility and power. This session asks:
How are dominant narratives formed and reinforced?
How can editorial work serve as a corrective or counterpoint?
What does it take to make space for genuinely different worldviews, without turning them into spectacle?
As with each session, the discussion will result in a two-sided poster—one visual, one textual—contributing to an evolving archive of situated editorial inquiry.
Editorial Studio 3 is a space to examine not only what we see, but how and why we see it the way we do—and what’s required to truly see from somewhere else.
Editorial Studio 4: Accessibility
これまでのセッションでは、イノベーション、矛盾、視点といったテーマが問い直されてきました。第4回目となるエディトリアル・スタジオでは、「アクセシビリティ(アクセス可能性)」というテーマに焦点を当てます——それは単なるインクルージョン(包摂)の問題ではなく、デザインのあり方そのものに深く関わる問いでもあります。
アクセスという言葉は、多くの場合、実用的な観点で語られます。たとえば、読みやすさ、手に入りやすさ、価格の手頃さ、見えやすさ——けれど、それらはあくまで表層的な条件に過ぎません。このセッションでは、次のような問いを投げかけます:
何が「アクセス可能」とみなされるのか?
その境界線は、誰がどのように決めているのか?
そして、デザインとリサーチはその定義にどのような影響を与えているのか?
テキスタイルとファッションは、これらの問いに取り組むうえで魅力的な枠組みを提供してくれます。衣服は親密であり、象徴的であり、構造的でもあります。それは社会的な規範、身体、経済を反映し、**布地は「見せる」と同時に「隠す」**という二重性を持ちます。システムを開くことも閉じることもできる。こうした文脈において、デザインは単なる表現の手段ではなく、「参加」あるいは「排除」の手段にもなりうるのです。
アクセシビリティは、必ずしも常に望ましいものでも、単純なものでもありません。このセッションでは、アクセスという概念がいかに媒介され、交渉され、争点化されるかに注目します。そして最後に問いかけます:
アクセスとは「与えられるもの」ではなく、「共に構築され、再解釈され、ときには抵抗されるべきもの」なのではないか?
August 3, 2025
efag.css (higashikasai)
Tokyo
detailed information about the session
- coming soon
Following earlier sessions that questioned innovation, contradiction, and perspective, Editorial Studio 4 turns its attention to the idea of accessibility—not only as a matter of inclusion, but as a deeply situated design question.
Access is often framed in practical terms: what is legible, available, affordable, or visible. But these are only surface-level conditions. In this session, we ask:
What counts as access?
Who defines the threshold?
And how do design and research shape those definitions?
Textile and fashion offer a compelling frame for these questions. Clothing is intimate, symbolic, and structural. It reflects social codes, bodies, and economies. Fabric both reveals and conceals; it can open or close a system. Design, in this context, becomes a tool not just for representation, but for participation—or exclusion.
Rather than assuming accessibility is always desirable or straightforward, this session asks how access is mediated, negotiated, and contested. How might we rethink accessibility not as something to be “granted,” but as something to be co-developed, reinterpreted, or even resisted?
Editorial Studio 5: Activating
これまでのセッションでは、「省察」「再定義」「再構築」といったテーマに焦点を当ててきましたが、第5回のエディトリアル・スタジオでは、実践へと視点を移します。今回のテーマは**「アクティベーション(活性化)」**。それは抽象的な概念ではなく、現実の社会状況に関わり、変化を促し、介入するための具体的でプログラム的なアプローチとして捉えられます。
文化理論家であり実践者でもあるヌライニ・ジュリアストゥティをリードに迎え、多様な分野からの参加者とともに、次のような問いを探ります:
何かを「活性化する」とは、具体的にどういうことなのか?
その実践が根付くためには、どのような条件が必要なのか?
文化、地域、制度的背景の違いによって、アクティベーションの手法はどのように変化するのか?
過去のセッションでは、「イノベーション」「矛盾」「視点」などの概念を、編集的かつ言説的な視点から考察してきました。対して、第5回では、実際の文化的実践を試す場として機能します。
文化的な仕事が、単なる批評や観察にとどまらず、組織化・共創・継続のかたちへとどう移行できるのか? を問います。
この対話では、「活性化」という言葉そのものの限界についても考察します。
誰が何を活性化するのか?
誰が活性化されるべきだと期待されているのか?
社会的な関与を「手段化」してしまうことのリスクは?
上から押しつけられた緊急性と、その場に根ざした自然な動きとを、どう見分けられるのか?
September 17, 2025
TBD
Kyoto
detailed information about the session
- coming soon
Following previous sessions that focused on reflection, redefinition, and reframing, Editorial Studio 5 turns toward action. This session explores the idea of “Activating”—not in abstract terms, but through grounded, programmatic approaches that seek to engage, transform, or intervene in social realities.
Led by cultural theorist and practitioner Nuraini Juliastuti, and joined by a diverse group of contributors, this session asks:
What does it mean to activate something?
What are the conditions that allow activation to take root?
And how do strategies of activation differ across cultures, geographies, and institutional contexts?
Where previous sessions explored concepts such as innovation, contradiction, and perspective through editorial and discursive lenses, Editorial Studio 5 is about testing modes of practice. How can cultural work move beyond commentary and reflection, and into forms of organizing, co-creating, and sustaining?
The conversation also examines the limitations of the word “activating” itself. Who activates, and who is expected to be activated? What are the risks of instrumentalizing social engagement? How can we distinguish between imposed urgency and situated momentum?
Editorial Studio 6: Surviving
「生きのびること」は、しばしば最も基本的な状態として捉えられます——政治よりも前に、美学よりも前に、構造よりも前にあるものとして。しかし、生存は決して中立ではありません。誰が、どのように生きのびるのか。それは常に、デザイン、インフラ、記憶、権力と深く結びついています。
本セッションでは、「生きのびること」を単なる持久力としてではなく、文化的・創造的・編集的な行為として捉え直します。それは維持であり、修復であり、変容であり、あるいは撤退かもしれません。ケアとして、即興として、静かな拒絶として現れることもあるでしょう。執着することでもあり、手放すことでもあります。
私たちは、「生きのびること」に対して「どう解決するか」を問うのではなく、それがいかに構築され、語られ、編集されるのかを問います。
このシステムにとって「エラー」と見なされる存在が、生きのびるためには何が必要なのか?生きのびる実践は、どんな痕跡を残すのか?そして、その痕跡が語りうる知は、どのようなものなのか?このテーマが問うのは、何が「生きのこるか」だけではありません。
生きのびるとは、何を要求することなのか—それを問うことなのです。
October 2, 2025
SKWAT KAMEARI ART CENTRE
Tokyo
detailed information about the session
- coming soon
“Surviving” is often thought of as the most basic condition—something before politics, before aesthetics, before structure. But survival is never neutral. Who gets to survive, and how, is always entangled with design, infrastructure, memory, and power.
In this session, we explore survival not as endurance alone, but as an active cultural, creative, and editorial gesture. Survival can mean maintenance, repair, transformation, withdrawal. It can look like care, like improvisation, like quiet refusal. It can be about holding on—or letting go.
Rather than asking how to “solve” survival, we ask how survival is shaped, narrated, and edited. What does it take to survive a system that sees you as a glitch? What traces do surviving practices leave behind? And what forms of knowledge are only visible after survival?
This theme asks us to think not only about what survives—but about what survival demands.